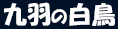-

-

-

-

-


-

- 原句は[帰り花夫と行く道引き返し]でした。
-

- 原句は[ 五線譜に雨の描きし冬景色 ]でした。
-

-

- 原句は[そぞろ寒七種の薬一気のみ]でした。
[ 目覚めよと鳥のそのこゑ神迎ふ]
[ ひとすじの光残して神還る ]
[ 空青く渡りの鳥のこゑを聞く ]
[大森理恵先生の御選評]
これは秋の季語の【鳥渡る】ですがやはり作者も仰ってますように、大好きな【渡りの鳥】ですから、、、ご投稿して頂きました。
この句の良いとこは上五の『空青く』と下五の『鳥のこゑ』と季語が上手く呼応しているとこです。このどれもが抜けてもダメなのです。俳句はたった十七文字の文藝。そこには重複させずに全てを詰めていくのが理想です。勿論①リズム②自己投影③映像の復元が大切ですが・・・ダイナミックな作品なので特選句に頂きました。
[ とんぼうの体いつぱい陽を浴びて ]
[大森理恵先生の御選評]
いよいよ11月!
あと一週間で初冬ですね。秋の季語の【蜻蛉】ほど別名の多い季語はない。【やんま】【のしめ】【秋茜】【あきつ】【えんば】【えんま】【とんぼう】それ以外に上に地名も付く色々な呼び方がある。それほど、日本古来、『神武紀』にも出てくる日本人が長い間、親しんで来たのであろう【蜻蛉】(我が角川源義師の亡くなられた忌日には師の大好きであった唄!必ず全員で♪夕焼け小焼けの赤とんぼ♪と『赤蜻蛉の唄』を合掌するのが恒例である)
挙げ句はとんぼうが秋の日を身体中に浴びている様子を詠んでいるがとても斬新な、一句である。蜻蛉と言うと、何か寂しい例句が多いが今回の作者の一句は、とてもおおらかに明るく【蜻蛉】を詠まれている。類想のない珍しい作品である。このような前向きな一句も大好きである。言葉もシンプルで誰にもわかる佳句。特選句に頂きました。
[ かすかなる着信音や冬に入る ]
[大森理恵先生の御選評]
京都は急に寒さが厳しくなりすっかり冬です。上五から中七までの『かすかなる着信音や』の措辞が季語の『冬に入る』と何とも言えず、【付かず離れず】でたまらなく、素晴らしい。
この季語の【付かず離れず】というのが非常に難しい。付き過ぎると説明句になる。付かな過ぎだと破茶滅茶な一句になってしまう。初冬に、大きな音のスマホの着信音は合わない。かと言って、仲冬、晩冬でも、無理がある。この繊細な感性や発想は作者らしい細やかな機微がありとても品格がある。この作者の特徴としてどの作品も上品で且つナイーブである。
上の挙げ句は【言葉は平明に想いは深く】という私の俳句哲学そのものの一句である。が、細やかで微妙なこの発想に季語の『冬に入る』の着地がピタリとハマって素晴らしい!!
昨夜から嬉しい事があり一睡も出来ずにみちのくの俳句のお友達と長い時間、電話で話しをしていた。彼女は俳句を学ばれて40年以上。然も二つの結社の同人さんである。彼女の選句はかなり良い。一昨日の【神還る】の作者の事も二年でこれだけの作品を作られるとは!!! と、大絶賛されていた。私も自分のお弟子さんながら、作者の上達ぶりには唖然である。
【ひとすじの光残して神還る】も大特選句であるが私は、こういった繊細な句も大好きである。勿論、初冬の特選句である。
[ 忘れ花夫と行く道引き返す ]
[大森理恵先生の御選評]
長い間のご夫婦の歳月、色々な出来事を乗り越えてこれまでの人生を共に暮らして手をとり合って来られたのであろう。️普通、下五の止めには『道進む』なのに原句の『道引き返す』この語彙には、正直、まいった。作者のご夫婦ならでこその、お言葉でもある。胸に熱いものが込み上げてきてジーンとなってきた泣泣泣
然もここでの季語の『帰り花』が凄く良い。此処は『道を引き返す」なので、同じ意味の『忘れ花』とした。あとは、流れ全体のリズムを少し整えた。ともかく、この一句はお二人の今までの道が超えた深い愛があることに感動した。羨ましい限りである!!!
こう言う【夫句】は作者の専売特許でもある。お優しくて太っ腹のお殿様のような作者の御主人の日々のことを伺っていると更に諾える。原句を大切にして少し、直させて頂いたがこの句も【自己投影】の最高の特選句です。
[ 五線譜に雨降る冬の景色かな ]
[大森理恵先生の御選評]
挙げ句の良いところは俳句に於いての貴重なエッセンスである『感性』と『発想力の自在さ』にあります。この画像が無ければ五線譜=水鳥の群れという画は、余程、長く、俳句を学んでないと浮かんで来ないと思います。が、この作者の若い瑞々しい感性により水鳥の群れ=五線譜に見立てられました。
これは、各自の自由な発想なのでそのように見れない方々がいらっしゃっても構わないのです。詩歌は自在な発想や感性=規制観念に押し付けられていない、藝術でもあります。️(添削したのは原句を一層、格調高く流れを整えて綺麗に見せる為に先ず、大切なリズムを整えました。)この句は一目見て特選句に頂きました。